Essay
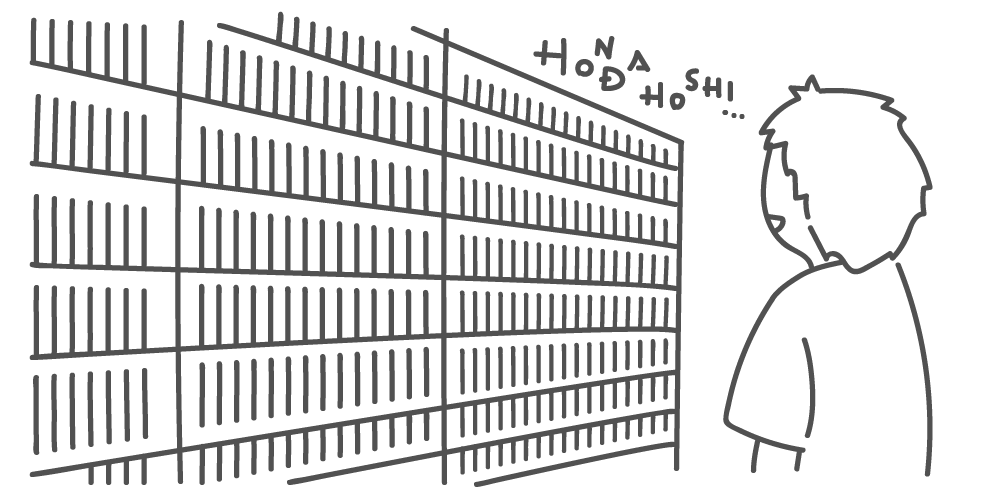
本棚と本
#27|文・藤田雅史
こうして本についての原稿を毎月書いているくせに、我が家には本棚がない。
本棚がないと何に困るかというと、当たり前の話だけれど、本の置き場に困る。本は、一度読んだら売る、あるいは捨てる、という人がいる(けして少なくない)。彼らは、「大事な本だけ手元に残して、あとは現金にしちゃった方がいい」と言い、きまって「モノが増えるのがいやだ」と付け加える。わかる。読み終わった本はとっておいても、どうせ二回も読まないのだ。世の中には古書店があり、ブックオフがあり、メルカリがあり、古紙回収がある。
これまでに何度か、そろそろ読まない本を処分してはどうか、と考えた。でも、結局できなかった。「いつかまた読むんじゃないか」「きっと役に立つときがくる」「この本は二度目の方がきっと楽しめる」そんなことをちらりとでも思いはじめるともうだめだ。売れない。捨てられない。
同じタイトルの本が単行本と文庫で二冊あったとき、そのうち一冊は売ってしまえばいいと普通の人なら考えるだろう。でも、やはり売れない。どちらを手元に残すべきか、考え始めるともどちらも売る気になれない。単行本はハードカバーの手触りが捨てがたいし、文庫は巻末に解説がついているからこちらも捨てられない。二冊を左右の手に持ちながら、「♪キライになれたらスゴク楽なのかなぁ?」なんてJUDY AND MARYの懐かしい歌のフレーズを思い出す。
目の前の本が全部、紙幣の束だったらいいのに、と思うことがある。同じ紙だ。お金の世界には「収支」という言葉があり、入る分と出る分をバランスよく調整して生活したり貯蓄したりするけれど、僕の場合、本は「収収」だから、ひたすら増える一方だ。収収。なんなら収々。中国のパンダの名前みたいである。本当に、1ページが1万円札だったらいいのに(なんなら千円札でもいい)。
今住んでいる家には、いちおう本棚と呼ぶべき木製のシェフルがあることにはある(それも複数ある)。けれどそれらは妻の本や雑誌、子どもの絵本などにすべて占領されていて、僕の本は自室で平積みの摩天楼と化す一方だ。暮らしはじめて十年なので、かなりの大都市に成長しつつある。このままだとメガロポリスになる日もそう遠くない。狭い家の狭いスペースに寝床と一緒に押し込められているから、大地震や有事の際は相当危険だ。最上階のこの『世界のレトロフォント大事典』が頭の上に落下したら。そう思うと、安心して夜も眠れない。妻からも「なんとかしたほうがいい」としきりに言われている。でも本棚がないのだからどうしようもないではないか。
本は家の中だけじゃない。事務所には仕事の資料となる雑誌や辞典が山積し、ここでも高層ビル群を作っている。実家にも学生時代の本が大量に残っていて、「早いとこ持っていってよ」と母にせっつかれている。先日、実家の押し入れの奥から『クレヨンしんちゃん』の全巻が出てきたと嘆きの電話があった。「ダンボールにぎっしり入っているのよ。すごく重いのよ」。全巻揃えた記憶がないが、そこにあるのなら、あるのだろう。
先週、メルカリでうっかりポチった『昭和ニッポン 一億三千万人の映像』というDVD付きの24巻セットが届いた。梱包を解き、思った。どこに置くんだこんなもの。そして考えた。いよいよ考えた。やはり、本棚が必要だ。よし、本棚を作ろう。
僕が事務所に使っているのは、三階建ての鉄骨の建物の一階部分で、今、三階のフロアが空いている。そこで、その三階を書庫兼書斎として使わせてもらうことにした。書庫。ショコ。寸足らずのチョコレートのような、甘い、いい響きだ。
せっかくだから本棚を造作してもらって、壁面を天井まで本で埋め尽くしてしまおう。Casa BRUTUSとか&Premiumで「本のある美しい暮らし」的な見出しがつきそうなお洒落系の本棚、本の隙間に置物や民芸品や植物が顔を覗かせる雰囲気系の本棚ではなく、実用優先、持ってる本を全部ぶち込んで、もう誰からも「本が邪魔」とは言わせない、そんな本棚を作ろう。うん、作ろう。そしてその本に囲まれて仕事をしよう。うん、そうしよう。
ということで建築家をやっている友人のTくんに相談して、一昨日、下見に来てもらった。「本棚がメインのフロアを作りたいんだよ!」と熱意を伝えると、「建物が、本の重さにどれだけ耐えられるか…」と冷静に切り返された。あまりにも重いと、床がたわむかもしれない、と。彼の表情から、あ、全部ぶち込むのは無理だ、と悟った。ぐぬぬ。そんな2020年の夏。
本棚づくりの話、そのうちまた続きを書きます。
■
