Essay
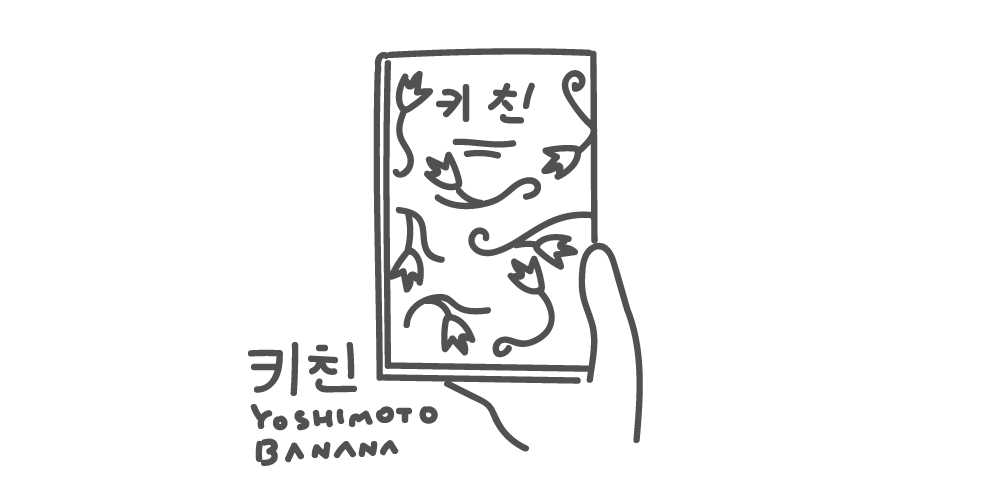
思い出と本
#40|文・藤田雅史
もうずいぶんと飛行機に乗っていない。子育て+コロナ禍で自由気ままな移動がほぼ不可能になり、我が家の家族旅行は、夏休みの山ごもりを除けば、「車で日帰り」がすっかり定番になってしまった。かつてお金と時間さえあれば格安航空券をサクッと買っていつでも気軽にできたはずの海外旅行は、いつのまにか「老後の夢」と化している。
あー、せめて一週間くらいかけて、ゆっくりと南の島とかに行きたいなあ……、なんて見果てぬ夢を見ながら、このあいだの日曜日、事務所の本棚の整理をはじめた。最近、人を招き入れることが増えたので、少しは綺麗に整頓しておこうと思ったのだ。見られて恥ずかしいものは見つからないようにどこかに隠しておこう、というのもある。まあ見られて恥ずかしいものなんてそんなにないのだけれど、ものを書く仕事をしている以上、来訪者から「うわ、この人バカっぽいなあ」と思われるのは避けたい。小さな男の、ちょっとした見栄である。未整理のダンボールから「魅惑のタヒチ」なんて本が出てきてうらめしい。
50音順にずらっと並べた文芸書の端の方、吉本ばななの本をゴソッと動かしているとき、日本語のタイトルに混じってハングルの文字が混じっているのに気づいた。白い装丁の、日本の四六判と同じサイズの上製本。代表作『キッチン』の韓国語訳である。
18年前、母と僕と、六つ年下の従弟との三人で、ウルムチとトルファンに旅をしたことがあった。海外登山やトレッキングを主に扱うツアー会社が企画した、初心者向けのライトなツアーで、シルクロードに憧れていた母の希望で実現した旅行だった。地元の空港から、韓国の仁川国際空港で飛行機を乗り継いだ。そのトランジットの待ち時間に空港内の本屋で見つけたのが、この韓国語版の『キッチン』だった。
大学時代、吉本ばななをたくさん読んだ。僕の通っていた大学は実は吉本ばななの出身校でもあるのだけれど、残念ながらまわりの友人たちは偉大な先輩の作品にまったく興味がないらしく、部屋にどさっと積んでいても誰も関心を示さなかった。それどころか「よくこんなの読むな」なんて言われて、ちょっと悲しい思いをしたこともあった。でも卒業が近づいてきた頃、ときどき部屋に来ていた友人のうちのひとりが、ふと思いついたように「そういえば試しに読んでみたけど、『キッチン』、よかったよ」と言ってくれた。そのひとことで、僕は『キッチン』が好きになった。
仁川の空港で見つけたその本を、僕は買った。当然、韓国語なので読めない。「いつか韓国語を学ぼう」と思ったわけではない。原文と訳文を比較してどうこうなんて面倒なことにもまったくが興味ない。「読まないとあらかじめ決まっている本」を買ったのは、はじめてだった。「買ったはいいものの結局読まなかった本」ならば腐るほどあるけれど、読まないつもりの本をわざわざ買うことはない。今思えば、そのとき僕は、本のかたちをした本ではないものを買ったのだと思う。「JAPANESE」と記された棚の、ハングル文字しか並んでいない中から適当に引き抜いた一冊が『キッチン』だったという、その偶然の喜びを胸にとどめておく、という行為を買ったのだ。
思い出す。開港して間もない広くて清潔な空港内の雰囲気。次の便までずいぶんと時間があって退屈だったこと。三人で交互に荷物の見張りをして、売店を隅から隅まで見て回ったこと。夜のフライトで北京上空から見下ろした夜景が綺麗だったこと。トレッキングのツアーなのに従弟がサンダルでやってきて、母に怒られていたこと。パオに泊まったら凍えそうに寒かったこと。ツアーの食事はどの店に行っても同じものばかり出てきたこと。写真をいっぱい撮ったこと。お土産に干しぶどうをたくさん買ったこと。楽しかった。
電子書籍というメディアが登場して、だいぶ経つ。それでもいまだに自分のスマホには電子書籍のファイルがひとつも保存されておらず、もっぱら本屋もしくはネット通販で紙の本を買い続けるのは、もしかしたら、手触り云々、紙をめくるリズムが云々、ディスプレイの光の眩しさが云々、といった問題ではなく、もっと無意識のレベルでの、一生のうちにひとつの人生しか体験できない人間としての、本能的な選択なのかもしれない。
本は本である前に「もの」だ。「もの」はいつだって、思い出を纏うことができる。
■
