Essay
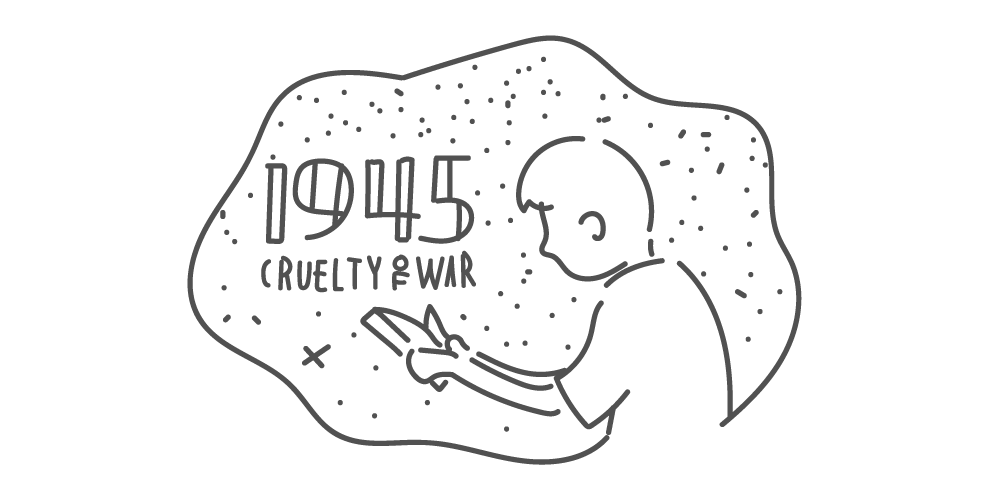
日本の夏と本
#52|文・藤田雅史
夏が終わろうとしている。朝晩の空気は秋のそれで、もうTシャツ一枚では肌寒く感じる。この夏はどんな夏だっただろう。新刊を上梓した。一年がかりで書き上げた小説だ。すべての作業を終えて、大きな解放感に浸った。でも大きなトピックスはそのくらいで、あとはいつもの年と同じ、いつも通りの夏だった。
さてこの数年、8月になるときまって昭和史に関する本を読みたくなる。8月といえば、1945年(昭和20年)8月の印象がとても強い。原爆、ポツダム宣言受諾、終戦の詔勅……日本の8月は、戦争の「追憶」のためにあるような気さえする。
ただ追憶といっても、1980年(昭和55年)生まれの僕にとって、それはリアルな記憶とは無関係だ。頭の中に浮かぶのは、漠然とした、あくまでテレビや映画によって蓄積された戦争の時代の「イメージ」に過ぎない。イメージの中のそれはやはり悲惨であり、酷たらしく、そして貧しい。想像の中で狭い袋小路に追い詰められ、焦燥と諦念に駆り立てられ、風景はどれも軍服と焦土と砂埃と死の色に塗られている。
クーラーの効いた涼しい部屋でジンジャーエールなぞをぐびと飲みながらページをめくり、「夏がやって来るたびにこういう本を手に取ることは、やはり防衛本能のようなものだろうな……」と改めて感じた。毎年同じ式典が繰り返されるように、同じようにメディアがそれを取り上げるように、そしてまた同じような問題で誰かが誰かを批難するように、本を読むことで「これを忘れてはいけない」と確かめ続ける。確かめ続けたい。そうしないと忘れてしまう。忘れると、繰り返す。その危機感だ。今年は、やけにその危機感が強い気がした。
昭和という時代は、映像の時代でもある。戦争の映像には圧倒的な力がある。ドキュメンタリーも映画も討論番組も、視覚ではっきりと戦争を知ることができる。巨大なきのこ雲も、軍艦に向けて一直線に降下していく特攻機も、追い詰められ崖から身投げする女性も、大地にうち捨てられた死骸も、あらゆる映像に力がある。今はモノクロの映像に色がついたりするし、CGでまるで戦機を操縦しているような感覚になれたりもする。映像はすごい。ただ、情報の量、深さ、伝達手段としての手軽さという点で、やはり本はなくてはならない存在だと思う。人間が人間の経験と感覚を語るのに(後世に残すのに)、最も適しているのが本だと思うからだ。本がなければ、きっと「戦争の記憶」は途絶えてしまう。
本が売れない時代、本屋さんが次々に閉店していく時代、それは、ただ本が好きな人たちにとってだけの不幸ではないと、確信に近く思っている。戦争の時代を経験したことのない人たちが物事を決め、時代を動かす今このとき、「経験」は、こうやって後世の人間が本を開き、知識を得ることによってしか思い出すことができない。
僕にとっては蝉の鳴き声を聞きながら昭和史の本を読むことが、平和を願い続けることだ。
■
本サイトのウェブ連載エッセイが、一冊の本になりました!「本とともにある、なにげない日常」を、ちょっとしたユーモアで切り取る、本にまつわる脱力エッセイ『ちょっと本屋に行ってくる。』現在好評発売中です。>>詳しくはこちら
藤田雅史『ちょっと本屋に行ってくる。』
issuance刊/定価1,540円(税込)

