Essay
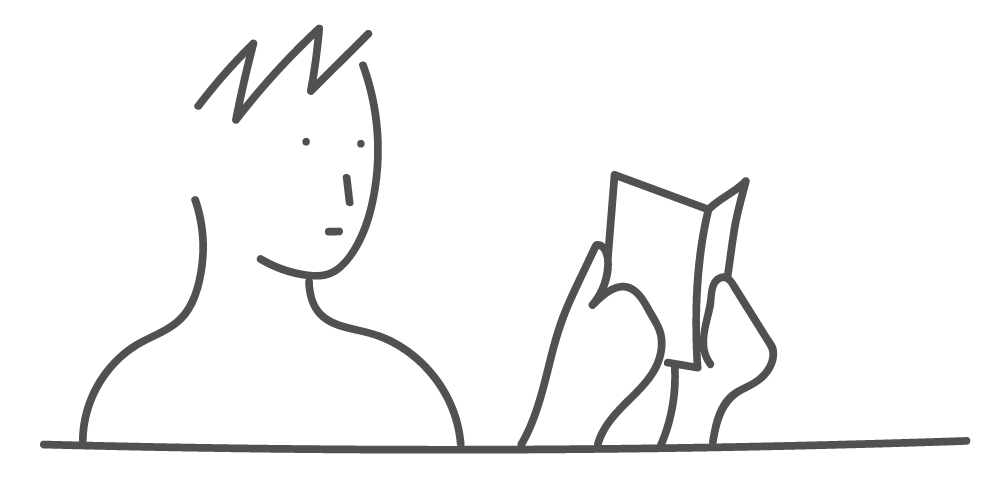
風呂と本
#01|文・藤田雅史
風呂は本を読むのに最適な場所だ。かつては就寝前の時間を読書にあてていたけれど、このところ仕事が忙しくて毎日帰宅が遅く、早く帰れたとしても子どもの相手や寝かしつけで疲れ果て、ベッドにもぐりこんで本をめくった途端、あっというまに眠りに落ちてしまう。仕事にも子どもにも邪魔されず、脳もいちおう覚醒していてリラックスできる場所、ということになると、もうトイレか風呂しかない。以前、同様の理由で風呂に夕飯を持ち込み、貴族的な優雅な晩餐を気取っていたことがある。当然妻には嫌な顔をされたが、時間の有効活用という点からは実に合理的で、これは共感を呼ぶ。そう思って友人たちに話したら、ほぼ全員にドン引きされたのでさすがに風呂での食事はやめた。
6枚の板からなる我が家の風呂の木製の蓋のうち、2枚を浴槽の左右に渡し、フェイスタオルを二つ折りで敷き、その上に本をのせて読む。二、三冊持ち込むこともある。換気扇は回しっぱなしで、寒くない日は少し窓を開ける。本を濡らすことはまずない。これが雑誌となると、薄いテカテカのコート紙が湯気を吸い込んで反り返ったりクシャクシャになったりしてしまうが、文庫本や普通のサイズの本の紙質なら問題ない。
ただ濡らすことがないかわりに、ときどき落とすことがある。
橋渡しをした板が知らぬまにずれて、手をついたり肘をついて圧を加えた拍子に浴槽の縁からつるりと滑落。あっ、と思ったときにはもう遅い。手に持って読んでいた本は咄嗟につかんで大事にいたらずに済むこともあるが、板の上に積み重ねていた本は湯の中へどぼん。いくら乾かしても、一度濡れた本はもう元には戻らない。かなしい。湯に溺れた物語はすべて悲劇だ。
先日、平日の日帰り温泉に行ったら、露天風呂で読書している男がいた。三十代後半とおぼしき、学生時代にラグビーやってましたみたいなガッチリとした筋肉の持ち主で、岩風呂につかりタオルを頭にのせ、女性が腕時計を見るようなポーズで片手に本を持ち、器用にページをめくりながらその世界に没入していた。
うらやましい、と思った。自分もそんなふうに堂々と、露天風呂で本を読みたい。自宅の風呂でさえいい気分なのだから、青空の下、広い露天風呂で読書など最高だろう。しかしその行動をまねる勇気はない。やはり浴場のマナーというものを気にしてしまうからだ。
どうなんだろう、温泉や銭湯に本を持ち込むのって。直感としては、だめだろう、と思う。でも本が湯を汚すことはない。誰かに迷惑をかけたり、健康を害するわけでもない。スマホを持ち込むのとは違うので隠し撮りの心配もない。そもそもこの国には湯船で酒を飲む危険な文化だってあるくらいだから、マイシャンプーやマイひげ剃りを持ち込むのと同様に、本くらいならいいんじゃないかとも思う。
しかし本といっても、いろいろある。例えば鄙びた地方の温泉の露天風呂でカバーの外れた文庫本、それも松本清張の短編集なんかを読んでいたら、なんだか絵になる気がする。風情すら感じる。でもそれが『ゼロからわかるマンガ財務諸表』だったら、どうだかな、と思ってしまう。『ワールドサッカーダイジェスト』。雑誌くらい風呂上がってから読めよ、と思う。サイズも問題だ。かといって文庫本ならいいかといえば、そうでもない。フランス書院文庫。やめてほしい。いろんなことが気になってしかたない。熟女系ヘアヌード写真集。周りがハラハラする。その露天風呂全体が、なんだか凄まじい空気になりそうで怖い。
ここまで考えてやっぱり本の持ち込みはだめだろう、と改めて思うのは、どうしても周りが気にしてしまうからだ。本を読んでいる人のそばではうっかりしぶきを立てられない。本人の意志とは無関係に、周囲の人間が過剰な配慮を強いられる。
マナーにはグラデーションがある。すべてはケースバイケースで、白と黒ではっきりと善し悪しを区別できるものではない。客の少ない温泉の片隅で推理小説を静かに読むのは結構かもしれないが、例えば週末の激混みのスーパー銭湯の大浴場で自己啓発本を堂々と読まれると、なんだかものすごく腹が立つ気がする。
それに本の持ち込みはよし、ということになると、うっかり上下巻を持ち込んで長湯し、救急車で運ばれるような迷惑な者が出てくるだろう。また、それをビジネスに転換しようと企画をこしらえる者も出てくる。「親子で集まれ!湯船で楽しむ絵本読み聞かせイベント」。いやなにもそれ風呂でやらなくても。
ちなみに、三十代後半の元ラガーとおぼしき青年が読んでいた本は、遠目からでもタイトルがはっきりと読み取れた。『WE ARE LONELY, BUT NOT ALONE.』。なんだか、誘われているみたいだった。
■
