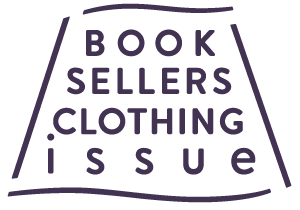Essay
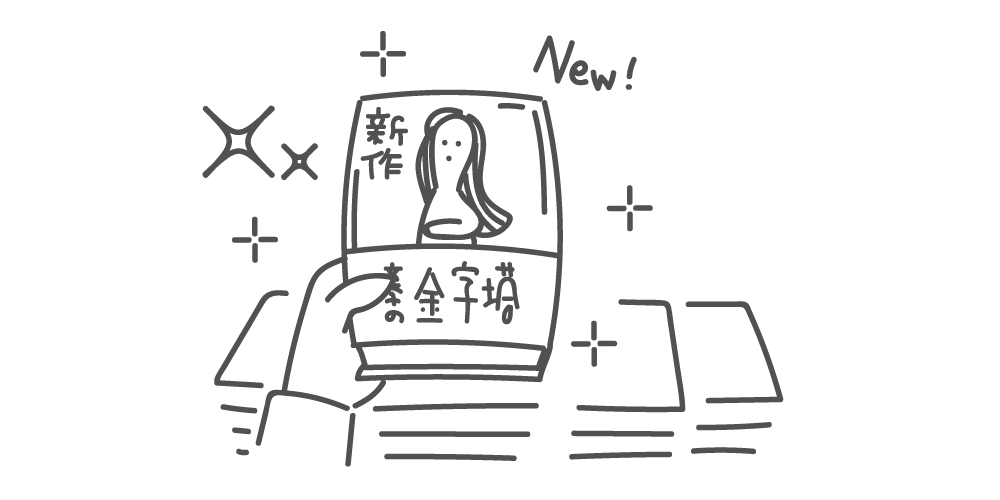
デジタルと本
#06|文・藤田雅史
ペーパーレス、という言葉が叫ばれて久しい。いや誰も叫んではいないのかもしれない。でも、電子書籍なるものが登場した頃から、あるいはそのずっと前、デジタルという言葉が当たり前の存在になったあたりから、「出版業界の危機だ!」と誰かが叫んでいるように見えた。聞こえた。そしてその叫びは今もずっと続いているように見える。聞こえる。
出版業界には詳しくない。でも実感として、とりあえず雑誌がやばい、というのはわかる。それまで定期的に読んでいた(立ち読みしていた)雑誌が、あれよあれよと書店から消えていった。週刊の雑誌が月刊になり、いつのまにか季刊・不定期発行となる流れは、じわじわ首を絞められる姿を傍観するみたいで哀しい。同時に、好きだった雑誌の内容がスカスカになり、記事が面白くなくなり、純広告がどんどんしょぼくなっていく様子を見るのはもっと哀しい。印刷業界で働く友人と話すと、雑誌だ本だという以前の段階で、「紙」や「印刷」の需要が以前よりもぐっと減っているという。
「みんな、ネットで済むよね。」そういう時代がきてしまった。で、自分はどうかというと、本は買っているが、やはり雑誌は買わなくなった。読まなくなったのかといえばそうではない。最近、コンビニに並んでいるような雑誌がどれもこれも読み放題というアプリを利用し、指先で紙をつまむのではなく、スワイプで雑誌をめくっている。毎週毎週、新しい雑誌が月額にすると週刊誌一冊分にも満たないような額で読めてしまうのだから、一度のこの便利さを体験すると、はっきり言ってよほど気に入ったものでもない限り、雑誌を一冊普通に買うのが馬鹿馬鹿しく感じてしまう。
音楽業界の現状もそれに近いのだろう。CDが売れない。CDと同じ音源がクリックひとつで瞬時に購入できて、さらには月額ほんのいくらを払えば膨大な数の楽曲が聴き放題になるとなれば、よほど好きなアーティストのCDじゃないともう誰もCDなんて買わないのではないか。買うとしたら、「音源」というよりも「グッズ」みたいな感覚に近づいてきている。こういう状況でなにより残念なのは、楽曲の作り手の収入が減って、ものづくりの質が下がることだ。「今までならここ、生楽器入れてたけど、打ち込みでいいよね。」的なことがどんどん増えて、お金をかけない曲作りが主流になる。選択肢が減ることで楽曲のクオリティが低下し、演奏者が食いっぱぐれ、誰も音楽の世界に夢を見なくなる。なんか、せつない。
さて、ではそれと同じことが本でも起こるのだろうか。誰も紙の本を定価で買わなくなり、かわりに印刷コストのかからない安価な電子データが読書の主流になり、しかもそれが読み放題になって作家のギャランティーが激減し、ひとつの作品にかけられる手間も時間も経費も情熱も削られ、質の低いものばかりが巷に溢れて「本ってべつにあってもなくてもどっちでもよくない?」みたいな時代が来るのだろうか。え、もう来ている? あ、いや、そんなことは…。
とここまで書いて頭を抱える。「ネット」というほとんどコストのかからない無限複製のできるメディアが発達したことで、このくだらない原稿もまた、その大きな流れの中での一滴として存在しているのは事実だ。本が好きなのに、本でも雑誌でもない、誰でもタダで読めて、読み終わったら何も残らない時間つぶしみたいなそんな原稿を書いている。普通に、当たり前のことみたいに。うーん。
でも、やっぱり本が好きだ。本屋で本を選ぶのが好きだ。今も昔もそうだけれど、自分の好きな作家の新刊本というのは、書店の棚や置き台でひときわ輝いて見える。新しい小綺麗なカバーを着せられ、どっさり平積みにされたものに出会ったときのあの幸福感。手に取ったときのあの重み。ぺらっとめくったときの本文用紙の清潔な指触り、純白ではない微妙なクリーム色の親しさ。きれいに並べられた書体の凜々しさ、行間のゆとり。裏の価格を見て「わ、今回1800円かよ、高いな…」と思いつつ、買う以外に選択肢のないちょっと悔しい感じや、「最高傑作」とか「金字塔」とか、そのフレーズこれまで何回使ってんだよと思うけれど、「まじか、じゃあ絶対読まなきゃ堪能しなきゃ」とうっかり欺されてしまう(欺されるのがすでに快感にもなっている)帯のコピーとの接し方は、まるで恋のかけひきのようだ。家に帰ってからじっくり読もうか、それとも帰りの電車の中で読みはじめてしまおうか、そのタイミングを自分の中ではかる感じもワクワクする。読みはじめたら面白くて止まらなくて、終盤にしおりや紐を挟むたび、「ああ、もうこれだけしか残ってない…」と寂しくなる日曜日の夕方みたいな感じも快感に近い。
内容うんぬん以前のこれらの感覚こそが、本だ、と僕は思う。本には、本を買う時間やルーティンの美しさ、喜びが含まれている。その価値は、「安くて便利」と等価かそれ以上のはずだ。なにより電子書籍を表示するデバイスに、まだ本物の書籍と同等の美しさは感じられない。その美的、空間的、時間的価値が実際の本を凌駕しない限り(人間の感性が変質しない限り)、本という存在はなくならないと信じたい。
そういえばだいぶ前に、貧しさとは何だろう、と考えたことがあった。そのときに出した答えは、「欲しい本を買えない状態」だった。食べ物を手に入れられない貧しさは、自分にとってのリアルじゃない。でも、本を買えない貧しさは、実際に起こりえるかもしれない。今になって思えば、本当に危惧するべき「欲しい本を買えない状態」とは、「本を買えない貧しさ」ではなく、「買う本のない貧しさ」の方なのかもしれない。
■