Essay
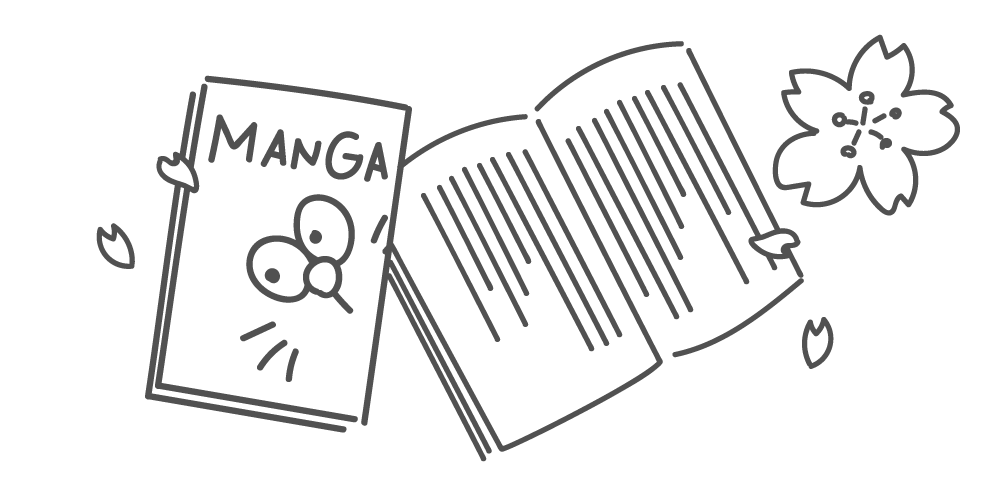
小学一年生と本
#11|文・藤田雅史
この春、息子が小学校に入学する。持ち物を準備したりそれに名前を書いたり通学路を覚えさせたり、なんやかや妻は慌ただしく忙しそうだが、当の本人はそれほど「不安と期待で胸がいっぱい」みたいな感じではなく平然としているし、僕もまた目の前の仕事に追われて、ああもう来週入学式か早いなあ、なんてふと思いながらこんな原稿を書いている。
六歳の息子は今「ドラえもん」と「ゾイド」にハマっていて、いつも夜寝る前に枕元でドラえもんのマンガを読むのが習慣になっている。特に僕が子どものときに買った「大長編ドラえもん」の原作マンガが気に入りで、「パパ、リトルスターウォーズ面白かったよ!」とか言われると、ようやく「父と息子」ではない、フラットな関係で話せることができるようになったみたいで嬉しい。「パパもスネ夫の家の庭のジオラマがすごくうらやましかった」「あーわかるよ」「撮ったものがミニチュアになる道具が欲しかった」「わかるわかる。あとスモールライトが欲しいよ」そんな感じだ。
ただ親として心配なのは、マンガにハマりすぎて、活字の本を読まなくなるのではないか、という点だ。マンガもいいけど、やっぱり本を読んで欲しい。絵本から一歩先に進んだ、挿絵のついた字の本を。でも、ときどき息子を本屋に連れて行って、「これ読んでみない?」と興味のありそうな恐竜などの活字の本を薦めてみるのだが、「いや、いらない」という素っ気ない返事ばかりで、どうもうまくいかない。
ところが最近になってようやく、「これ欲しい。パパこれ買って」と息子が活字の本を所望した。ドラえもんの映画の最新作「のび太の月面探査機」の小説だ。脚本を担当した辻村深月が描き下ろした小説のジュニア版で、手にとってめくってみると挿絵のない純粋な活字の本だった。(読めんのか…?)と心配になるほど活字がびっしりだった。対象年齢はおそらく小学校の中学年以上だろう。まあでも本人が読みたいと言っているのだからこれはチャンスと思って買い与えた。
小学一年の春に、挿絵のない文字だらけの本はキツいと思う。なかなか読み進まない。でも、寝る前に少しずつ読んでいるようなので、父親としてはその姿が頼もしく、嬉しい。思えばマンガだって最初は(マンガなんて読めるのか?読み方わかるのか?)と思っていたけれど、いつのまにかスラスラ読めるようになったわけだし、すぐに活字の本にも慣れるだろう。
で、ふと思ったのは、はて自分が小学一年生のときに何を読んでいたんだろう、ということだ。僕がマンガを読みはじめるようになったのは小学二年生くらいからで、その記憶は確かにある。ではその前は何を読んでいたんだろう。
幼稚園の図書室のようなところに、「エルマー」のシリーズがあったのを覚えている。「エルマー」はたしかシリーズが三冊あると記憶していて、その記憶の感触は「ドラゴンボール」や「コロコロコミック」よりも古いから、おそらく幼稚園から小学一年生の頃だと推測される。実家の本棚を思い出しているうちに、だんだんとそれ以外の記憶も戻ってきた。寺村輝夫の「王さま」シリーズが好きだった。「おばけのはなし」も。「はれときどきぶた」とか、「二ちょうめのおばけやしき」のシリーズも読んでいた。「ズッコケ三人組」シリーズを集めていたのは何年生のときだろう。宗田理の「ぼくら」シリーズは高学年で、その頃はシャーロック・ホームズや江戸川乱歩の怪人二十面相シリーズも読んでいた。
名作と呼ばれるようなものや、クラスや図書館で人気のあるような本にはほとんど興味がなくて、自分の好きな本だけがひたすら好きだった(今とちっとも変わらない。ちゃんと古典に接したことはないし、流行のベストセラーもまずは手を伸ばす気にならないたちだ…)。人を好きになるときに、その人の全体が好きになるように、僕は本のたたずまいが好きだったんだろうと思う。かたち、色、表紙の絵、もちろん内容もそうだけれど、好きな本はその本全体が好きだった。好きな本は、自分だけが見つけた、自分が守ってあげたい、そんな気持になった。好きな人ができるずっと前から、好きな本がいつもそばにあった。
今、こうやって勢いまかせにだらだらと「書くこと」を仕事の一部にできているのは、きっとそのおかげなのだと思う。本が好きで書くことに憧れた。書くことの勉強や努力なんて何もしないで、憧れだけでずっとやってきた。「本」が好きなのではなくて、「好きな本」が好きなんだと思う。やっぱり人と一緒だ。「人間」が好きなんじゃない。「好きな人」が好きなのだ。
息子にも、そういう本と出会って欲しいと思う。人の出会いが一生ものなのと同じように、本の出会いだって一生ものだから。
■
