Essay
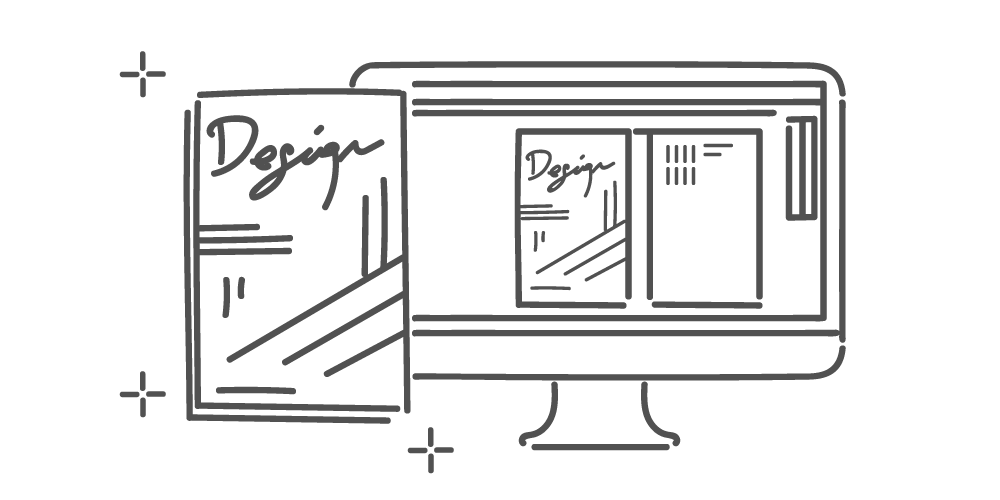
デザインと本
#12|文・藤田雅史
本というのは、読んでみなければその価値がわからない。けれど読む前から「ああ、これは絶対に好きな本だ」とわかってしまうときがある。たまに、ではなく、しばしば、ある。書店で手に取ったとき、あるいは見つけたとき、あ、と感じる。その予感はほとんど外れることがない。これは面白いに違いないと思いながらワクワクしてページをめくり、そのワクワクが最後まで続く。
あの予感はなんなのだろう。と、お気に入りの小説やエッセイを思い浮かべてしばし考え、なーんだ、とその理由にあっさり気づいた。本のデザインがよいのだ。ここでいう「よい」というのは、あくまで個人的な「よい」であって、つまりデザインが「自分好み」ということ。例えば、最近のベストセラー本でいえば平野啓一郎『マチネの終わりに』の、あの青と黄色の装丁。大胆で、繊細で、美しく滲み合う箇所の絶妙な切り取り方。これは面白いに違いないと、確信を持って手に取った。そして面白かった。こうしたジャケ買いならぬ装丁買いにほとんどハズレはない。
そこで気になるのがブックデザイン、あるいは装丁をする人の仕事だ(ちなみに『マチネの終わりに』は石井正信さんという方がデザインをされています)。以前、好きな本を並べてその装丁のクレジットを見たら、みんな同一人物によるデザインだった、ということがあった。有名なブックデザイナーの鈴木成一さんの仕事だった。鈴木成一さんは『装丁を語る』『デザイン室』といった著書で、ブックデザインの舞台裏を解説されている。内容がこうだから、こういう装丁になった、ということがわかりやすく説明されていてかなり興味深い。(ついでに言うと、ワークスコーポレーション刊『BOOK DESIGN』という大きめの本も装丁好きの方にはおすすめです。)
よくよく考えてみれば、まず優れた内容の原稿があって、優れたデザイナーがそれを読み込んでアイディアをかたちにすれば、優れたデザインが仕上がるというのは割と筋の通った話だ。デザインはコミュニケーション、という観点からしても、「これはいい本だよ」というメッセージが作者→編集者→デザイナー→読者とダイレクトに伝わるから、「ああ、これは絶対に好きな本だ」と書店で表紙を見ただけでピンとくるのだろう。デザイナーが意図して絞ったターゲットの設定、アイディア、印象操作に、自分がどんぴしゃでハマってしまった(見事、目論見通りに落とされた)、ともいえる。素晴らしい仕事だ。
ところで個人的に、第一印象でグッときてしまう本の傾向、というのがある。人に例えれば、「好きなタイプ」というやつ。背が低くて細身で丸顔、みたいな。
ひとつは大胆な色づかい。白石一文の『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』の単行本(文庫ではない)上下巻のような、ピンクとグリーンの絶妙な補色の対比。東野圭吾の『白夜行』のような黄色に白タイトルという抜け感が凄すぎるインパクトのある配色。あるいは真っ白とか、真っ黒とか、真っ赤とか。何に惹かれるって、その潔さだ。この本はこの色!というブレのなさが、なんだか作品の「自信」や「自負」を胸を張って表現しているような気がするのだ。
それから、イラストや絵を、白地などに清潔にすっきりと配置するシンプルなスタイルも好きだ。これは吉本ばなな『体は全部知っている』の文庫が、マイベスト。浅田次郎『姫椿』の文庫も、マガジンハウスから出た川上弘美『ざらざら』の単行本もかなり好みだ。この手のデザインは優れた短篇集に多い。余白の美しさが絶妙で、凜とした風格や雰囲気がある。
あとは、装丁の全面に使われている絵やイラストや写真が、それだけでもう気に入ってしまう場合。大崎善生『孤独か、それに等しいもの』の表紙絵、山崎ナオコーラ『ニキの屈辱』の表紙写真、津村記久子『浮遊霊ブラジル』の表紙のイラストレーション。こういった「うわ、これ好き」というビジュアルを目にすると、裏表紙の値段も見ずにそのまま手にとってレジに直行だ。まさに装丁買い。もし、自分の好きなピーター・ドイグの絵を表紙に使っている本があったら、1ページもめくらずに僕はそれを買うと思う。
そうそう、思い出したけれど、原田宗典の本の多くは大御所デザイナー原研哉さん(たしか作家の高校時代の同級生)の手によるもので、とても憧れた。ちなみに新潮文庫の原田宗典の本は背表紙がシルバーで、そういうちょっとしたこだわりにグッとくる。
本は、そんなふうにただ見るのも楽しい。
■
