Essay
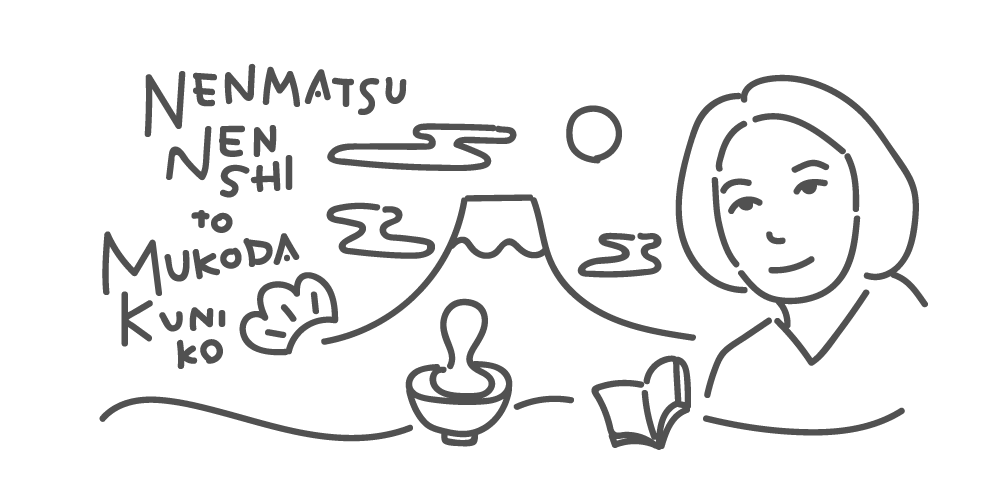
年末年始と本
#20|文・藤田雅史
暮れの大掃除を、この年末はいつもよりも大がかりに時間をかけておこなった。ほとんど家宅捜索のような気分で断捨離にのぞみ、10年近く手つかずだった納戸の奥をあらためたり、何が入っているかわからないダンボール箱を片っ端からひっくり返したりしていると、出るわ出るわ。あちこちから埃をかぶった本がたくさん出てきた。
買ったけれど読んでいない本、読んだけど内容をまったく覚えていない本。出てきた本は、だいたいがその二種類に分けられる。どちらも内容に覚えがない。なぜ買ったかすらわからない本もある。「あれ?これ、前に買ってたんだ…」と、最近になって買った本と同じものを見つけることもある。自分の記憶力が他人より著しく劣っているのではないかと疑うのはこういうときだ。(世の中の皆さんは、買った本や読んだ本の内容って、覚えていられるんだろうか?)
我が家には大きな本棚がない。無印良品のスタッキングキャビネットを2箇所で本棚として使っているのだけれど、ひとつは子どもの絵本やマンガに、もうひとつは妻の読む本や雑誌に専有されていて、自分用の本棚がない。本棚がないとどうなるかというと、資料に埋もれる文豪しかり、少年ジャンプを買い続ける中学生しかり、本はひたすら積み重ねられていくことになる。
文庫は文庫、新書は新書、四六判は四六判で大きさを揃えて重ねていかないと、本の山は途中で崩落する。そろそろ天井に届きそうな本のタワーが摩天楼のように連なる姿は、本好きの僕からすれば壮観な眺めであるけれど、妻の口から出るのは「危険」のひとことだ。
さて、休みのあいだは時間があるからじっくり本を読もうと意気込んで、去年の暮れもいつものように仕事納めの後で書店に立ち寄り、来たるべき未来を語るようなビジネス書や分厚いミステリー、この一年のベストセラーの中でずっと気になっていたものなど、一度にたくさん本を買い込んできた。でも、年末年始は意外と本を読める時間が少ない。忘新年会で酒を飲めば頭が働かず、大掃除をさぼるわけにもいかず、親戚と会ったり子どもたちの遊び相手をしているうちに三が日はあっという間に過ぎていく。そばや餅を食べて糖質摂取過多になり、重たくなった身体を横たえると、なんだかページをめくるのが面倒くさくなり、本を読むより箱根駅伝をぼうっと見ていた方がいいや、となってしまう。来たるべき未来のことは正月が明けてから考えればいい。ミステリーは本の厚さに尻込みをし、ベストセラーも買っては見たが実はたいして興味ない本だったりする。結局あまり読まなかった、というのがいつものパターンだ。
しかし今年は、年末年始にちょうどいい本を見つけた。買い込んだ本が手つかずだったかわりに、大掃除で発掘した向田邦子の短篇をめくってみたところ、これが年末年始の雰囲気にぴたりときた。新潮文庫の「思い出トランプ」と、文春文庫の「隣の女」。どちらもちょうど、僕が生まれた頃に編まれた作品集だ。
昭和50年代の家族。男女。日本の一般家庭の風俗。湿った古い畳の匂いを嗅ぐような懐かしさは、里帰りをして実家の押し入れから抜き出した写真アルバムを眺める感じに似ている。昔を懐かしむと同時に、家族の知らない一面を垣間見て、妙な距離を感じるような。家族であっても知ることのない、ひとりひとりの胸の内を覗きこむような。そこに映っているのは父と母だが、見知らぬ男と女に見えるときもある。
三が日を過ぎたらまだ持っていない向田邦子の本を買いに行こう、と思いつつ、でも来年の年末年始用に買わずにとっておこう、とも思う。そういえば「思い出トランプ」は学生時代にも読んだから、これまで三回くらい買い直しているかもしれない。そろそろ大きい本棚を買って本をちゃんと整理しよう。目の前の高層ビル群のどこかに、「阿修羅のごとく」も「寺内貫太郎一家」も「父の詫び状」も隠れているはずなのだ。
■
